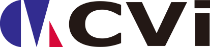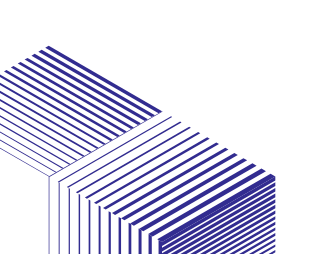勤怠管理システムの失敗例から学ぶ導入成功のためのポイント
政府主導の働き方改革に対応するため、多くの企業が社員の労働時間や労働環境を細かく把握できる勤怠管理システムの導入を進めています。
ただ、社員の勤怠状況は企業によって千差万別です。勤怠管理システムを導入してみたのは良いものの、社内に定着せず、結局元の方法に戻したり、別のシステムを導入することになったりするケースも少なくありません。
そこで今回は、勤怠管理システムの導入を成功させるために知っておきたい、よくある導入失敗例をご紹介します。
勤怠管理システムが求められるようになった背景
多くの企業が勤怠管理を求めるようになったのは、簡単にいうと働き方改革に対応するためです。働き方改革に対応するためには、社員の労働時間を把握し、上限以上の残業をしないよう働き方をコントロールする必要があります。
ただ、タイムカードを手作業で集計していると、PCの起動など客観的な勤務実態に合わせて出退勤を付け、月の労働時間が一定のラインを越えたら作業を止めるよう通知を出すといった対応をするのは困難なので、勤怠管理システムの導入が進んでいるのです。
勤怠管理システムを導入した際の失敗例
会社の規模や勤務形態に合っていなかった
勤怠管理システムは、サービスによって想定している会社の規模や対応できる勤務形態が違います。小さな企業が大企業向けのシステムを導入すると機能を持て余してしまいますし、逆に大企業が中小企業向けのシステムを選んでしまうと、十分な勤怠管理ができません。
コストを抑えて小規模な勤怠管理システムを導入した結果、変形労働制・シフト制・裁量労働制・直行直帰・独自の休暇制度など、自社の働き方に合う勤怠管理の機能がなかったため、勤怠管理システムの乗り換えが必要になったというケースも多いです。
機能をうまく使いこなせなかった
非常に高機能な勤怠管理システムを導入したにも関わらず、社員が使いこなせなかった、会社に定着しなかったという失敗例もあります。
優れた機能があることと、それを使いこなせるかどうかは全く別の話です。シンプルなシステムでも、社員に対する十分な講習がなかったり、マニュアルがわかりづらかったり、導入担当者がうまくフォローできなかったりすると、「勤怠管理システムを使う」という文化が社内に根付きません。
給与計算や人事管理などほかのシステムとうまく連携できなかった
勤怠管理システムのデータ形式と、給与計算・人事管理といったその他のシステムで使えるデータ形式が異なり、システム間の連携ができなかったという失敗例もあります。
勤怠管理システムの目的は、集計したデータを給与計算ソフト等に流し込み、給与計算や人事管理を効率化することです。
データの受け渡しができないとシステムを導入するメリットが薄れてしまうので、勤怠管理システムを導入するときは、その他システムとの相性も考慮する必要があります。
サポートが不十分だった
勤怠管理システムをサービスとして提供しているのは、民間のプロバイダです。
- 導入時の説明がわかりづらい
- 機能について要望や質問をしたが返答が遅い
- 法改正後のアップデートや機能追加がない
- 販売元が数年でサービスの提供を打ち切った
など、安心してサポートを受けられない状態だと長く使えません。
勤怠管理システムは、全社員が利用するシステムです。何度もシステムを乗り換えると社員に負担をかけるので、サポート体制が充実したシステムを選ぶ必要があります。
勤怠管理システムの導入を成功させるためのポイント
自社の勤怠管理に合ったシステムを選ぶ
勤怠管理システムを導入するときは、自社の就業規則や勤務形態に合ったシステムを選びましょう。
出退勤の打刻ができるだけでなく、細かい休憩や休暇の申請・承認にも対応できるのか、社員や場所に合わせて複数の打刻方法を選べるか等をチェックすることが大切です。
トライアルや事前の問い合わせでシステムの機能面を把握した上で、導入を進めましょう。
社員が使いやすいものを選ぶ
勤怠管理システムは、あくまでも社員が使うものです。打刻や申請に時間がかかったり、UIが分かりづらかったりすると、入力ミスが増えますし勤怠管理システムの浸透にも時間がかかります。
せっかく勤怠管理システムを導入しても、適切に運用されなければ意味がないので、勤怠管理システムを取り入れるときは現場の社員や勤怠管理業務の担当者の意見を聞き、評価の高いものを選びましょう。
他のシステムと連携できるか確認する
勤怠管理システムを選ぶときは、給与計算システムなどの他のシステムと連携できるか事前に調べておくことが重要です。
データ形式はもちろん、データを受け渡す際の流れや出力のしやすさをチェックしておけば、導入後の混乱を最小限に抑えられます。
サポートが充実したサービスを選ぶ
勤怠管理システムの成功は、社員が慣れるまでサポートできるかどうかにかかっています。
普段の業務をしながら触ったことのない勤怠管理システムの設定を行い、運用しつつ社員のフォローをするのは大変です。
導入初期につまずくと取り返しがつかないので、勤怠管理システムを選ぶときは、サポートの手厚いサービスを選びましょう。
法改正に対応可能か確認する
法律は毎年のように改正されます。法改正に合わせて機能や設定をアップデートしてくれるシステムでないと、担当者が手作業で設定を変更することになるため、負担が大きいです。
人の手で行う作業を減らすことがミスの予防にもつながるので、勤怠管理システムを選ぶときは、法改正に応じてアップデートしてくれるものを選びましょう。
まとめ
勤怠管理システムの導入は、全社員に影響を与える取り組みです。単にシステムを用意するだけでは、自社の勤怠管理に必要な機能がなかったり、現場に合っておらず社員が使いこなせなかったり、給与計算等のシステムと連携できなかったりする可能性があります。
勤怠管理システムの導入を成功させるためには、製品の吟味や導入初期のサポートが必要不可欠です。どのシステムでも同じ結果を出せるわけではないので、機能面やサポートの充実度をチェックして、自社に合う勤怠管理システムを取り入れましょう。